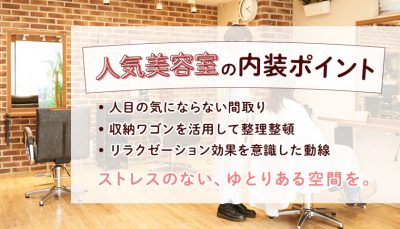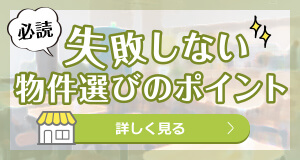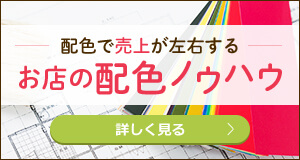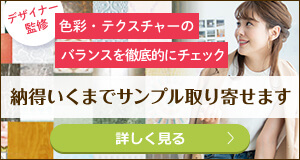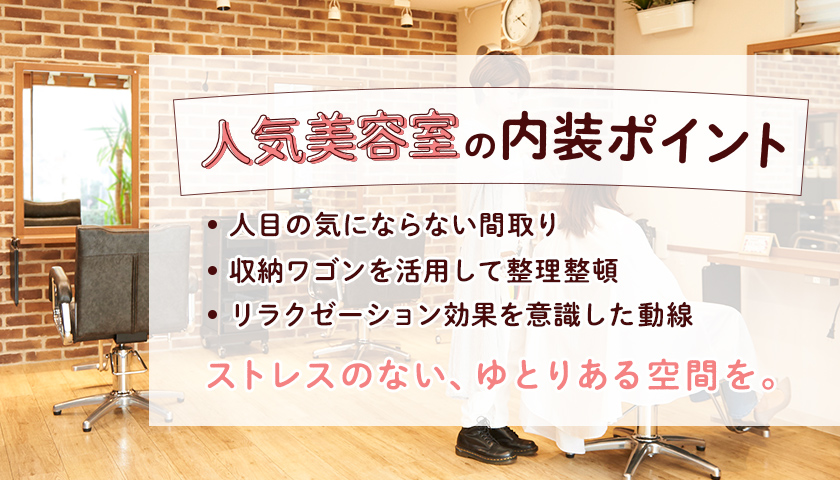「近所にできたあのお店、自分のお店とデザインが似ている?」と感じながら、どう対処して良いかわからず、不安なまま過ごしている店舗オーナーも多いのではないでしょうか。
様々な思いを込めて作った店舗デザインが、他人から真似されてしまった時のショックや悲しみは計り知れません。
店舗の内装や外観デザインを模倣された時に備えて、店舗デザインの「意匠権」に関する法の動きを知っておきましょう。
2019年から店舗デザインも「意匠権」で守られるように
「意匠権」とは、製品の形、色、模様などが、他人から侵害されることを防ぐ権利です。
意匠権は、デザインを発表して6カ月以内に特許庁に申請することで取得でき、一度取得した後は、登録から20年まで効果を持ちます。
店舗のデザインも意匠権で保護されようとしている
これまで、店舗の内装・外観デザインは意匠権の範囲に含まれていませんでした。しかし、政府は2019年に「意匠法」の改正を検討しており、改正後は店舗の内装・外観デザインも意匠権の範囲に含まれます。なお、意匠権の期間も、現行の20年から25年に延長される見通しです。(2018年現在)
店舗デザインが意匠権で保護されるのはなぜ?
アメリカ合衆国では、店舗の内装や外観、制服や陳列方法などを「トレードドレス」とし、各企業の知的財産として法律で保護しています。トレードドレスの保護によって、国内の他企業だけでなく、海外企業によるブランドの模倣も防ぐことができ、ブランドの唯一性を世界規模で確立することも不可能ではありません。
店舗デザインを意匠権に含めようという動きは、国内企業の成長を後押ししようという考えも含まれています。
店舗の内装デザインが似てしまう原因
店舗の内装は、故意に模倣していなくても似てしまうケースがあります。ご自身の店舗デザインが模倣されたか判断に困った時は、以下の事例に当てはまらないか確認してみましょう。
店舗と相性の良い色にはパターンがある
色はそれぞれ特定の効果を持っており、店舗の内装デザインでは、色それぞれの効果が使い分けられています。例えば、飲食店なら「赤は食欲をそそる、青は食欲が減退する」などのように、使うべき色、避けるべき色は共通しています。
また、多くの人に安心感を与える配色にも定番のパターンがあります。茶色や緑など、自然を彷彿とさせ安心感を与える「アースカラー」は、店舗の内装デザインでは業種を問わず人気があります。ピンクやパープルを組み合わせた「パステルカラー」も、若者が好むポップなお店で多く見かける配色パターンです。
このように、一定の客層に対して効果が高い色が偶然似てしまうことは、同業種であれば珍しいことではありません。
万人に好まれるデザインには共通点がある
和風のお店なら、のれんに筆文字のロゴ、瓦屋根や木製の面格子を外観や内装に取り入れるといった具合に、デザインにはセオリーが存在します。セオリーに従った結果デザインが似てしまっても、ある程度仕方がないと言えるでしょう。
また、同時期に開業したお店であれば、流行のデザインが偶然似てしまっても不思議ではありません。
店舗デザインの意匠権は過去にも問題になっている
これまで店舗の外観や内装は意匠権では保護されていませんでしたが、他の企業のデザインを故意に模倣した場合は、「不正競争防止法」に違反するとみなされるケースもありました。
有名な例では、大手喫茶店チェーンの「コメダ珈琲」が、店舗の外観や内装、制服などを模倣されたとして、喫茶店会社に対しデザインの使用中止と損害賠償を訴えた事例があります。
しかし、不正競争防止法では、デザインの独自性や新規性が厳密に定義されておらず、店舗デザインが模倣されたことの立証は容易ではありませんでした。今後、意匠法が改正すれば、店舗デザインの独自性についての定義が明確になり、企業が自社ブランドをより守りやすくなるでしょう。
意匠権は「創作非容易性」を満たすことが条件
一般的に誰でも思い付くようなデザインを、何でも意匠権で保護してしまうと、後からデザインする人は何も作れなくなってしまいます。
そのため、意匠権の取得には「簡単に真似できず、創作性が高いこと(創作非容易性)」を満たすことが条件の一つとなっています。
デザイン会社に内装デザインを委託した場合の意匠権は?
店舗デザインを、デザイナーなどの外部業者に委託した場合に、お店のオーナーとデザイナーのどちらに意匠権があるか、トラブルになることがあります。
デザイナーが店舗から委託されてデザインを作った場合は、デザイナーに「意匠登録権」が生じます。従って、お店のオーナーがデザインの意匠権を取得するためには、業務委託契約の際に、「意匠登録権をオーナーに譲渡する」などの項目を盛り込んでおかなければなりません。
おわりに
デザインの模倣は、どこまでを模倣とするか、判断が非常に難しい問題です。
万が一、店舗デザインを明らかに模倣された時に、自社のブランドを守って客離れを防ぐためにも、意匠法改正の動きをよく理解しておきましょう。