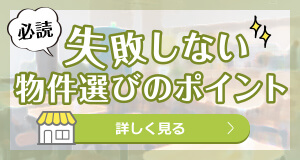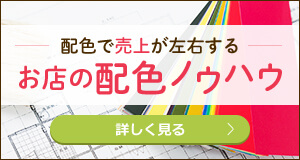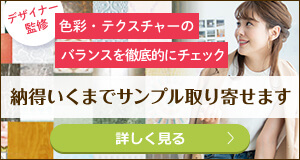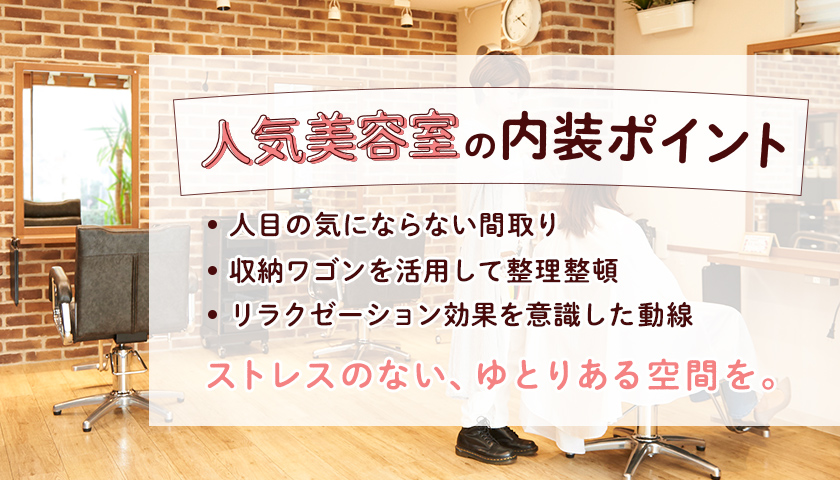外食はよく耳にしても、「中食」という言葉には馴染みがない方も多いのではないでしょうか。
いま、外食でも内食でもない中食の市場規模が増えつつあります。
この記事では、中食の定義や代表的な種類をご紹介するとともに、中食の需要が高まっている背景についてご紹介します。
中食とは?
「中食(なかしょく)」とは、「外食」にも「内食」にも該当しない食事のスタイルを指します。
外食とは、お店でメニューを注文して食べるスタイルのことです。
内食(うちしょく)は、野菜や肉などの材料をスーパーなどで買って、自宅で調理して食べることを意味します。
そして中食は、お店でも食べず材料を調達して自宅で調理もせず、調理済の料理を自宅で食べるスタイルを指します。
中食にはどんな種類がある?
中食の例を挙げると、以下のようなものがあります。
● コンビニのお弁当
● スーパーやデパ地下のお惣菜
● 冷凍食品
● ピザやお弁当のデリバリー
● テイクアウト商品
など
コンビニのお弁当やテイクアウトフード、デリバリーフードだけでなく、調理をする必要がない餃子やチャーハンなどの冷凍食品も、中食に含まれます。
実は今、食品業界では中食の市場規模が拡大しています。

中食の需要が高まっている3つの背景
中食には、
● 材料を買わなくていい
● 家庭内で食材の無駄が出ない
● 調理に時間をかけなくていい
● お店まで移動する必要がない
● 自宅で本格的な料理が味わえる
● 外食に比べると安い
といった数々のメリットがあります。
これらメリットの存在こそが、現代社会に中食が受け入れられている大きな理由です。
中食は最も「時短」な食事スタイル
現在は、仕事以外の時間を副業やダブルワーク、資格取得、スキルアップなどに有効活用する人が増えています。
また、共働き夫婦にとって、帰宅後の家事の時間は少しでも減らしたいものです。
しかし、いくら調理をする暇がないと言っても、時短のために外食を続けていればお店まで移動する時間もかかり、食費もかさんでしまいます。
一方、中食は食材を買ってレシピを考え、自宅で調理する必要がないため、圧倒的な時短効果を発揮します。
お店までの移動費もかからず、店内で注文して食べる料理に比べるとお惣菜やお弁当の方が安く済みます。
コンビニ利用者の年齢層が広がっている
中食業界はコンビニによって支えられていると言っても過言ではないでしょう。
コンビニは24時間どの店を訪れても、お弁当やおにぎり、冷凍食品が販売されており、仕事が遅く料理をする時間がない方でも利用できます。
現在は、各コンビニが「プライベートブランド」の開発に力を入れており、ハンバーグや焼き魚、サラダや晩酌のおつまみといった、家庭の食卓を意識した食材も増えています。
このようなプライベートブランドの存在も手伝って、以前までは10~30代が中心利用者層だったコンビニも、40代以上や60代以上のリピーターを増やしつつあります。
中食の品質が向上している
中食ブームが訪れる前のテイクアウト商品や持ち帰りのお弁当などは、味も鮮度もレベルが高いとは言えませんでした。
揚げ物はべちゃべちゃ、野菜や魚などの生鮮食品は鮮度も味もイマイチ、おにぎりは水気でふやけ、麺は容器の中で絡まっている…、こんなお弁当やお惣菜を食べてがっかりした経験のある方も多いのではないでしょうか。
現在のお惣菜やお弁当は、味も見た目も10年前に比べると遥かにレベルが上がっています。
食感や鮮度が長持ちする製法や調理方法、保管方法が研究され、揚げたてのような食感のカツや餃子、ふっくらしたお米、麺をほぐす精製水付きのうどんなども登場し、できたてとほとんど変わらない味が家庭でも楽しめるようになりました。
市場規模が拡大している中食業界は狙い目?
晩婚化や核家族化により、中食を多く利用する単身世帯や高齢者世帯がファミリー世帯の数を上回りつつある昨今、これから飲食業界に出店しようと考えている方とって、中食分野への進出は狙い目と言えるでしょう。
しかし、中食が発展した背景である「時短」と「高品質な料理」という要素を守るためには、注文後にすばやく高品質な料理を提供できる、独自の体勢を整えなくてはなりません。
ここで言う高品質には、「食の安全性」という意味も当然含まれます。
中食を「お店で作った料理をお客さんに持ち帰ってもらうだけ」などと考えていては、激戦区と化しつつある中食業界で生き残ることは難しいかもしれません。
中食リーディング企業のこだわりを知る
年に数千万円や数憶円の売上を出している中食のリーディング企業はいずれも、
● 添加剤や着色料などを使わないこと
● 食材の無駄を出さないこと
● 出来立ての鮮度を保つこと
に重きを置きながら、店舗の効率化や新商品開発、食材の仕入れルート確保などに尽力しています。
ブームという理由だけで中食に手を出そうとは決してせず、こういったリーディング企業の取り組みなどを勉強して、中食業界の知識を付けておくことが大切です。
おわりに
中食の利用者は以前よりも増え、今後も増加傾向は続くと見られており、中食産業への進出は有望と言えます。
しかし、多くの人が手軽に中食を楽しめるようになった理由は、既存の中食ブランドが料理の品質を向上させたことも大きく影響しています。
これから中食産業への参加を検討している方は、中食リーディング企業の取り組みをよく勉強しておきましょう。