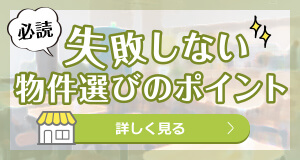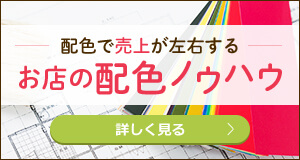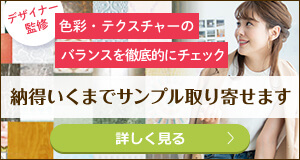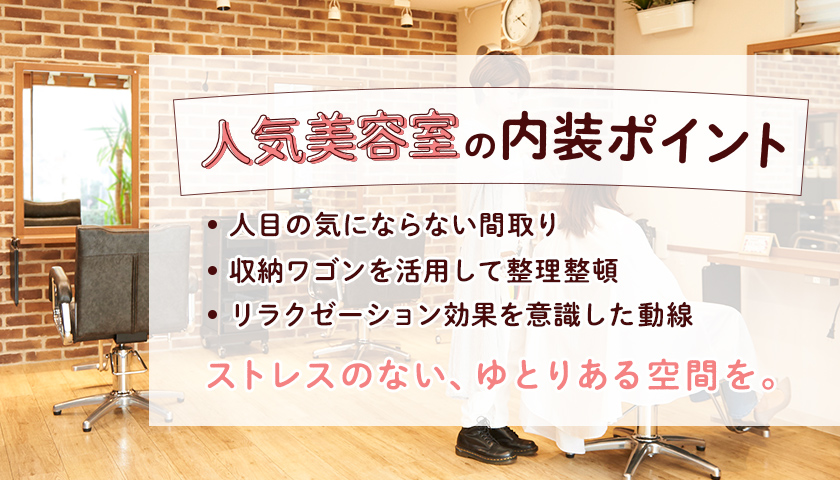万が一、ケガや病気で医療機関を利用したとき、医療費の一部を負担してもらえる制度が、健康保険です。
会社に勤めているあいだは、会社の社会保険に加入していますが、退職した後は自分で健康保険の加入手続きを行うことになります。
この記事では、退職後に加入できる健康保険の4つの選択肢と、選ぶときのポイントについて解説します。
退職後は健康保険の手続きが必要
日本に住んでいる限り、なんらかの健康保険に加入していなければなりません。
すなわち、会社を退職して社会保険を脱退した時は、社会保険以外の健康保険への加入手続きが必ず発生します。
健康保険の加入手続きは難しくない
個人で行う健康保険の加入手続きは、初めて経験する人は誰でも不安になってしまうものです。
しかし、健康保険の手続きは、自分が加入できる健康保険の種類さえわかっていれば、所定の窓口で手続きを済ませるだけで完了します。
まずは、退職後に加入できる健康保険の選択肢と、それぞれの加入手続きが行える窓口を知っておきましょう。
退職後の健康保険の4つの選択肢

退職後に加入できる健康保険には、以下4つの選択肢があります。
社会保険の任意継続をする
任意継続とは、退職した会社の社会保険を、2年間継続できる制度のことです。
利用するためには、前の会社の社会保険に2カ月以上加入していなければなりません。
また、加入手続きは、退職した本人が退職から20日以内に行う必要があり、自動的に適用されるものではありませんのでご注意ください。
なお、保険料は退職時の「標準報酬月額」をもとに、自治体ごとの料率で計算されます。
国民健康保険に切り替える
個人事業主や次の会社が決まっていない人など、どこにも雇用されていない人は、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の加入手続きは、お住まいの自治体の市役所や支所で行うことができます。
保険料は、前年度の収入から経費を差し引いた金額で計算されますが、個人事業主の場合、退職した次の年は、会社員時代の給与をもとに計算されます。
家族の社会保険の被扶養者になる
夫や妻、両親など、家族が会社に勤めている人は、家族の社会保険の扶養に入ることができます。
ただし、扶養に入るためには、自身の年収が130万円以内であり、家族の収入の2分の1以内であることが条件です。
また、個人事業主でも家族の扶養に入ることができます。
扶養家族が何人いても、保険料は1人分ですので、開業直後で経営が軌道に乗るまでの手段として検討するとよいでしょう。
なお、個人事業主も、経費を差し引いた所得が130万円以内であることが扶養の条件になりますので、経営が軌道に乗るころには、個人で健康保険に加入しなければなりません。
文芸美術国民健康保険に加入する
『文芸美術国民健康保険組合』は、デザイナーやイラストレーター、作家のほか、映画や音楽などの文芸全般に携わっており、かつ、職種ごとの団体に属している人が加入できます。
組合員になった人は、文芸美術国民健康保険(文美国保)が利用できるようになります。
組合に加入するためには、
・日本国内に住所があること
・75歳未満であること
・障がい認定を受けていないこと
・会社の健康保険に加入していないこと
が条件です。
保険料は定額で、組合員1人につき月額19,600円です。
加入手続きは、所属団体の加入証と、確定申告書の控えのほか、自身が手掛けた作品の資料を添えて、組合へ提出します。
健康保険を選ぶときのポイント
家族の扶養に入る選択肢を除いて、どの健康保険でも、毎月保険料を納めなければなりません。
また、どの健康保険が相応しいかは、本人の収入や扶養家族の有無などによって変わるため、業種が同じ人でも、同じ健康保険が適しているとは限りませんのでご注意ください。
健康保険料は大きな負担
健康保険に加入すると、約1~2万円前後の保険料を毎月納めることになります。
たとえその差額が3000円でも、1年間では36,000円もの差になりますので、加入している健康保険の見直しも時には必要です。
最も保険料が安くなる選択肢を見つけよう
国民健康保険の場合は、前年度の収入で保険料が計算されます。
また、社会保険の任意継続を選んだ場合は、標準月額報酬が、保険料の計算根拠となります。
そのため、退職したばかりの個人事業主で、収入が前年度から大きく減った人は、この2つの選択しを選ぶと、保険料の支払いが重い負担となる恐れがあります。
一方、文美国保は保険料が定額になるため、前年度の収入に振り回されることはありません。
ただし、家族の中に、健康保険に加入していない人がいる場合は、家族1人につき月額10,300円が追加されます。
つまり、扶養家族が多い人は、世帯あたりの保険料が、国民健康保険に加入したときよりも割高になる恐れがあります。
以上の点を比較しながら、月々の保険料が最も安くなる選択肢を探していきましょう。
おわりに
健康保険制度は、日本国民であれば必ず加入しなければなりません。
退職後に慌てて手続きを行う事態にならないように、退職前に、ご自身が加入できる健康保険の種類を、4つの中からピックアップしておくことをおすすめします。
もし、月々の保険料の納付が厳しいときは、家族の扶養に入る選択肢も視野に入れるなどして、有利な立ち回りを考えていきましょう。