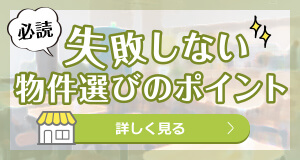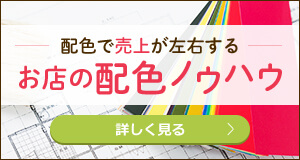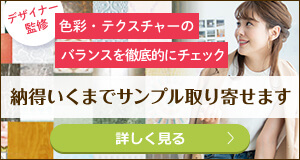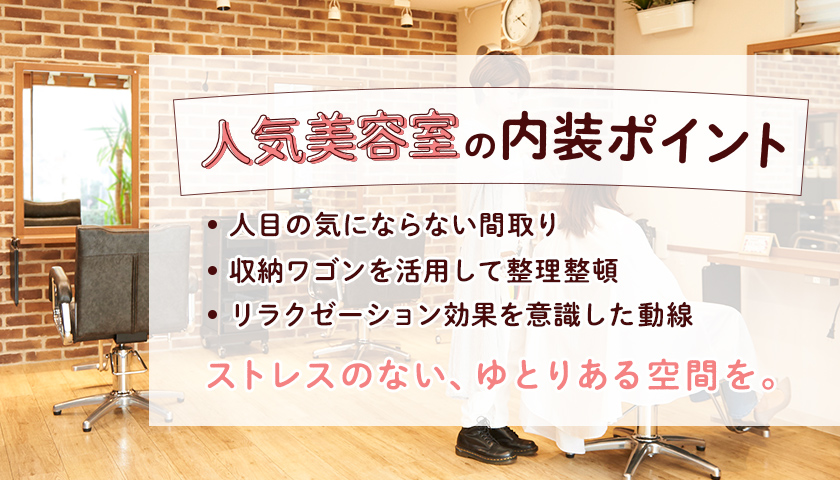会社員のあいだは社会保険に加入できますが、退職すれば、その資格を失います。
そのため、会社を辞めて個人事業主になった人は、国民健康保険への切り替え手続きを行わなくてはなりません。
この記事では、社会保険と国民健康保険の違いや、切り替え手続きの方法、国民健康保険以外の選択肢などについて解説します。
社会保険と国民健康保険の違い
「社会保険」とは、サラリーマンなど事業所で働く人が加入する、健康保険のことです。
なお、この記事で解説する社会保険は、様々な保険の総称である「社会保険制度」ではなく、会社員の健康保険とします。
「国民健康保険」は、会社員や公務員など、事業所や組合が用意した保険のいずれにも
加入していない人を対象とする医療保険です。
フリーランスや個人事業主は、自ずと「国民健康保険」に加入することになります。
日本に住むすべての人は公的医療保険に加入する
社会保険と国民健康保険は、どちらも、公的医療保険です。
すべての日本国民は、公的医療保険に加入しなければならず、これを「国民皆保険制度」と呼びます。
そのため、何かの医療保険を脱退した時は、必ず他の医療保険に切り替え加入の手続きを行わなくてはなりません。
個人事業主になったら「国民健康保険」へ切り替えを
会社員時代は、「社会保険」に加入していますので、退職するということはすなわち、社会保険を脱退することになります。
しかし、すべての日本国民は何らかの公的医療保険に加入していなければなりません。
そのため、会社員を辞め、個人事業主やフリーランスになった人は、「国民健康保険」への切り替えが必要です。
なぜ選択肢が自ずと国民健康保険になるかというと、国民健康保険は、会社員が加入する社会保険、公務員が加入する共済組合など、いずれにも加入できない人が唯一加入できる保険であるためです。
個人事業主になる人は、仕事を辞める前に、必ず健康保険の仕組みを学んでおきましょう。
国民健康保険は自治体が運営している
医療保険のうち、健康保険や共済保険は、協会けんぽや健康保険組合など、各種協会や組合が運営しています。
国民健康保険の運営は、お住まいの自治体が行っています。
そのため、新たに国民健康保険に加入する時は、自治体の窓口で手続きを行うことになりますので、会社ではなくご自身で窓口に赴かなければなりません。

国民健康保険への切り替え方法
社会保険は、会社を退職した日の翌日が資格喪失日となります。
国民健康保険に加入していない状態で医療費が発生すると、全額自己負担しなければなりません。
切り替え手続きは、退職日から14日以内に必ず済ませておきましょう。
ただし、国民皆保険制度によって、資格を喪失した時点で、特別な手続きを行わなくても強制的に「国民健康保険」に加入することになります。
そのため、無加入のまま保険料を支払わずに済ませることはできず、手続きを行っていなくても、保険料の納付義務は発生するのでご注意ください。
国民健康保険の加入は自治体の窓口で
国民健康保険への切り替え手続きは、お住まいの自治体の役場で行います。
市役所や支所などの健康保険の窓口に行けば、記入方法を説明してもらえます。
手続きでは、主に以下の書類が必要です。
● マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
● 身分を証明するもの(運転免許証、パスポートなど)※マイナンバーカードがあれば不要
● 社会保険の資格喪失証
自治体によっては、保険料の口座振替手続きがその場で行われますので、金融機関のキャッシュカードや、通帳と届出印も忘れずに持参しましょう。
国民健康保険以外の3つの選択肢
会社員や公務員以外の人が加入できる医療保険は、国民健康保険だけではなく、また、ご自身が必ずしも加入する必要はありません。
職業やライフスタイルに合った種類を選ぶことで、国民健康保険よりも保険料を抑えられることがありますので、3つの他の選択肢も知っておきましょう。
社会保険の任意継続
会社を退職しても、20日以内に任意継続の手続きを行えば、退職後も2年間は、会社の社会保険に継続して加入することができます。
国民健康保険の保険料が高額になってしまう方などは、最高限度額が設けられている任意継続の方が、保険料は安くなります。
ただし利用できるのは、退職した会社の社会保険に2カ月以上加入していることが条件で、手続きは、会社ではなく退職者本人が行わなければなりません。
文芸美術国民健康保険に加入
作家やデザイナーなど、文芸に関わる団体に属している人は、『文芸美術国民健康保険組合』に加入することができます。
その組合員が利用できる健康保険が、文芸美術国民健康保険(文美国保)です。
家族の社会保険の被扶養者になる
もし、会社勤めの家族がおり、かつ、ご自身の収入が家族の収入の2分の1(上限130万円)であれば、家族の会社の扶養に入ることができます。
被扶養者には保険料は発生しませんので、個人事業を開始したばかりで収入の見通しがない時は、扶養を検討すると良いでしょう。
国民健康保険以外の選択肢について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
退職したら忘れずに手続きを!健康保険の4つの選択肢を知ろう | 内装ハック 店舗内装やデザインの参考サイト
おわりに
日本国民は、必ず医療保険に加入しなければなりませんので、保険の仕組みは、生活する上での必須の知識と言えるでしょう。
退職後は、退職の後処理や事業を開始の準備などで何かと忙しくなりますが、忘れずに、国民健康保険への切り替え手続きが行えるように、退職前にある程度準備を進めておきましょう。