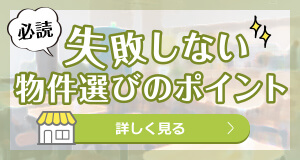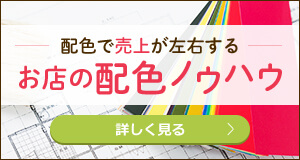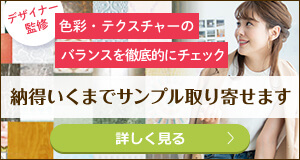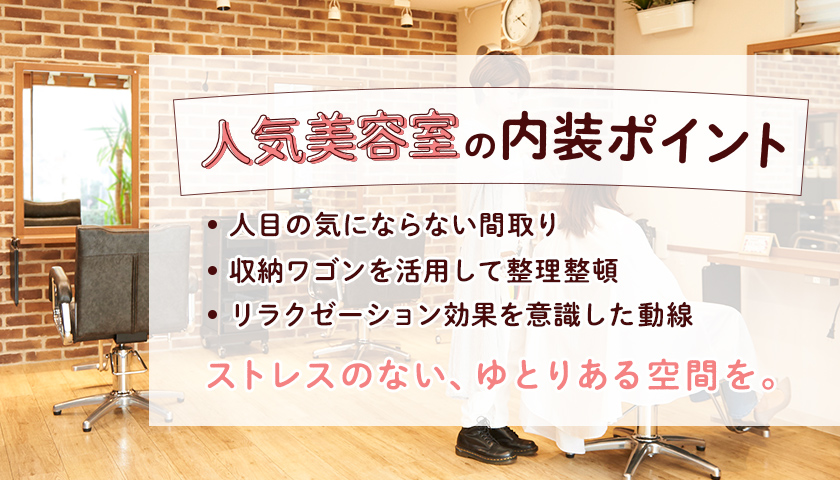目次
退職金が存在しない個人事業主にとって最大の悩みは、事業終了後の生活の保障ではないでしょうか。
そこで退職金の代わりとなるのが、今回ご紹介する小規模企業共済です。
節税効果など多くのメリットがある一方で、制度の内容を理解していなければ、デメリットしか残らないこともありますので、加入前に、内容をしっかり理解しておきましょう。
経営者の退職金制度「小規模企業共済」
「小規模企業共済」とは、個人事業主が廃業した時や、小規模企業の経営者が退職した時に備えて、あらかじめ積み立てておく制度です。
運営元は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)で、主に中小企業向けの融資や助言といった支援事業を展開する、国の一機関です。
個人事業主の退職後の代わりとして
個人事業主は、基本的に、退職金というものが存在しません。
しかし、小規模企業共済に加入していれば、廃業・退職時には、積み立てた掛金や期間に応じた給付金を受け取ることができますので、実質、退職金を受け取るのと同じ状態になります。
仕事を辞めても退職金がもらえない個人事業主にとって、退職後の大きな備えとなるでしょう。
小規模企業共済の内容やもらえる共済金について
小規模企業共済は、条件を満たして一定期間積み立てを続けた後、退職時に共済金を受け取ることができます。
「小規模企業共済」に加入できる条件
小規模企業共済は、以下A~Dのいずれかに該当する人が加入できます。
A.建設業、製造業、運輸業、宿泊業、娯楽業、不動産業、農業など
・常時使用する従業員の数が20人以下
・個人事業主または会社等の役員
B.卸売業、小売業、宿泊業・娯楽業を除くサービス業など
・常時使用する従業員の数が5人以下
・個人事業主または会社等の役員
C.企業組合、協業組合
・事業に従事する組合員、または従業員の数が20人以下
・役員
D.農事組合法人
・常時使用する従業員の数が20人以下
・農業の経営を主とする役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
もらえる共済金の種類
小規模企業共の共済金は、受取時の状態に応じて4種類に分かれています。
● 共済金A…個人事業を解約した時、加入者が亡くなった時に受け取り可能
● 共済金B…180カ月以上掛金を支払っている、65歳以上の人が受け取り可能(老齢給付)
● 準共済金…個人事業の法人化によって解約する時に受け取り可能
● 解約手当金…任意解約の時、または掛金の滞納により機構解約となった時
※個人事業主の場合

個人事業主が小規模企業共済に加入する3つのメリット
退職金の代わりとしてだけでなく、小規模企業共済には、加入することで得られる様々なメリットがあります。
掛金は経費扱いできる
小規模企業共済の掛金は、経費として計上でき、個人事業主であれば所得から控除されます。
つまり、個人の預金口座に月々貯蓄をするのと違って、小規模企業共済で積立をすると、所得税の節税効果を得られるようになります。
共済金にも節税効果がある
共済金は、分割、または一括で受け取ることができますが、いずれの場合も所得控除が適用されます。
通常、会社などから支給される退職金は課税の対象ですが、退職後の生活を安定させるためのお金ということもあって、税負担が軽くなるよう、「退職所得金控除」が用意されています。
個人事業主が共済金を一括で受け取った場合、受取金は退職金と同じ扱いになりますので、退職所得控除によって翌年支払う所得税を抑えることができます。
また、分割で受け取った場合は、退職金ではなく、「公的年金等の雑所得」として扱われますので、同様に節税効果があります。
様々な貸付制度を利用できる
掛金の額に応じて、中小企業基盤整備機構が用意している、様々な貸付制度を利用できるようになります。
貸付制度には一般貸付や疾病災害時貸付、事業場系貸付など、事業を行う上で便利なものばかりですが、どれも金利が非常に低いという特徴があります。
個人事業主が小規模企業共済に加入する2つのデメリット
小規模企業共済は、加入期間や解約時のリスクを把握できていなければ、節税という大きなメリットの効果を失ってしまう恐れがあります。
解約方法によっては掛け捨てになってしまう
小規模企業共済は、任意解約して解約手当金を受け取ることもできます。
しかし、積立期間が1年未満の場合、解約手当金は支払われませんので、掛け捨てとなってしまいます。
元本割れのリスクがある
掛金の全額が受け取れるようになるのは、20年後(240カ月後)からです。
つまり、20年以内に任意解約してしまうと元本割れしてしまいますので、加入前に、全額受け取りになるまでの期間を逆算しておく必要があります。
おわりに
小規模企業共済の共済金は、退職金がない個人事業主にとって、退職後の保障になるという点で重要な意味を持ちますが、事業継続中の節税効果という、さらに大きな効果もあります。
ただし、積立期間が20年以内だと、掛金の一部を失ってしまい、節税効果のメリットも無くなってしまうため、リスクもしっかり把握しておかなければなりません。
退職後の備えとして、ご自身にとって最も相応しい方法かどうか、よく検討したうえで選びましょう。